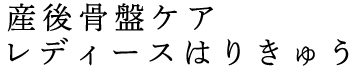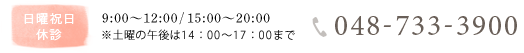軟産道強靭とは、赤ちゃんの通り道である産道のうち軟産道と呼ばれる部分が非常に硬く、赤ちゃんの移動を妨げてしまう場合を指します。
産道には骨産道(骨盤など骨で構成されている部分)と軟産道(筋肉や腟など軟らかい組織で構成されている部分)の2種類があります。どちらも出産の進み方や難産になるかなどに大きく関わってきますが、骨産道はほとんど形が変わらないのに比べ、軟産道は広がりやすいという特徴があります。
分娩中に赤ちゃんがおりてくるにしたがって、骨ではない軟産道は形を変えていきます。
しかし、なかには軟産道が非常に硬く、赤ちゃんの移動を妨げてしまう場合があります。
軟産道には子宮と腟が含まれており、それぞれが軟産道強靭の原因となりえます。
子宮は大きく分けて子宮体部と子宮頸部がありますが、多くのケースは子宮頸部によるものです。
●原因
大きく分けて器質的(物理的に広がりを邪魔しているものがある場合)と機能的(物理的な原因はないが広がれない場合)とに分けられます。
●器質的原因
子宮筋腫や子宮頸部の瘢痕(はんこん)などがあります。
子宮筋腫は子宮にできるコブで、これが大きい、もしくは多数あると、赤ちゃんが子宮から出てくるのを邪魔してしまいます。
子宮頸部の瘢痕は、初期の子宮頸がんなどに対して行われる子宮頸部円錐切除術の影響により、切除部分が治る過程で硬くなってしまうために起こります。
●機能的原因
子宮頸部や腟が分娩中に軟らかくならず、なかなか分娩が進まない場合に診断されます。
たとえば、高齢での初回分娩時などに起こります。通常は分娩が開始してから診断されるものですが、なかには予定日を過ぎても陣痛が来ない場合に、子宮頸部が硬いことから診断されることもあります。
●症状
お母さん自身の症状は特にありません。
しかし、軟産道強靭があると分娩がなかなか進まず、次第に子宮の筋肉が疲れてくることで微弱陣痛となってしまったり、その結果として遷延分娩や分娩停止となってしまったりする場合があります。
こうなると、長時間の陣痛となりお母さんも辛いですし、赤ちゃんも苦しくなってきてしまうことがあります。
もし分娩開始前に子宮頸部が非常に硬く、予定日を過ぎてしまった場合には、人工的に子宮頸部を広げる処置が必要になることがあります。
●検査・診断
主に内診と分娩経過による総合的な判断で軟産道強靭と診断されます。
特別な検査は必要ありませんが、子宮筋腫の場合には、事前に超音波検査で筋腫の位置や数、大きさを確認しておきます。
●治療
基本的に出産のゴールは赤ちゃんが無事に産まれることなので、これを目指して治療が行われます。
もし子宮筋腫が原因で分娩が全く進まない場合には、帝王切開以外に治療法はありません。
つまり、帝王切開術が必要になります。
このような帝王切開術のケースでは、子宮筋腫が邪魔になって通常よりも難しい手術になる可能性があります。
また、一般的には帝王切開術のときに子宮筋腫を同時に取ってしまうことはできません。
妊娠中の子宮は血流が多いため、子宮筋腫をとることでさらに出血が増えてしまうためです。
帝王切開術は出血量の多い手術であるため、ゆっくり丁寧に子宮筋腫を取っている時間がないからです。
子宮頸部が硬く分娩の準備が進まない場合には、人工的に子宮頸部を広げる処置を行います。
これは、子宮頸部に医療用のスポンジや水風船を入れることで、徐々に広げていくものになります。
ただし、この処置は陣痛が来る前にしか行えません。
陣痛がきて分娩が始まったのになかなか進まず、腟の軟産道強靭と考えられた場合には、子宮収縮促進剤(分娩促進剤)を点滴から投与することで陣痛を強め、どうにか軟産道が広がっていくことを期待することもあります。
腟の軟産道強靭がある場合、会陰(えいん)部分も硬くなっていることもあり、分娩時の会陰裂傷が大きくなってしまう可能性があります。会陰裂傷は分娩後すぐに縫合しますが、傷が大きい場合には時間がかかったり、痛みが強くなってしまったりする場合もあります。